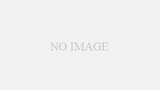全空連の公認段位二段にチャレンジしました!
そして1回落ちましたが、なんとか合格!!ポイントとかあるのでしょうか?
ちなみに公認段位という全空連の段位というものがあります。二段になると指導者資格が狙えたり、三段になると審判資格が狙えたりします。
2度めですが今度は合格!私が考える秘訣とポイントを記載します。
1.前回の審査について
全空連(全日本空手道連盟)の公認段位資格である段位を公認段位と言いますが、二段を取得すると審判資格や指導者資格に挑めるなど、指導者を目指す上では必須の資格になります。
初段の合格率が7割〜8割程度と言われますが、二段は5割〜6割程度と聞きます。
とまぁ、前回も似たような事を書いたので、過去記事を見てください。
で、前回落っこちて合格するために行った事や気にするべき点というかポイントや秘訣などを書いていきたいと思います。
ご参考になればと思います。
2.公認段位二段に合格!その秘訣とポイント
前回落っこちたのですが、そこから何をどう改善して今回は合格したのか?というのを書いていきたいと思います。あくまで私の場合ですので、ご参考程度にお願いします。汗
まず大前提として
2−0・方が下手だった!!
形が下手だったから落ちた!!
訳なので、形を練習し直すというのがまず第一です!
これは間違いない!
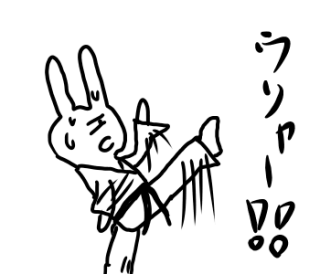
2−1.服装(空手衣)を変えた!
原因の1つ目、空手衣が合っていなかった!
ちゃんと自分の形用の空手衣を買った
前回は借り物の足の長さが長過ぎるということで、審査の先生たちに違和感を持たれたことでしょう。違和感は形の審査にも悪影響を与えた可能性があります。
なので、しっかりと今回は形用の自分用にカスタマイズしたものを使用しました!
とはいえ、師範からはまだ丈が長い!と言われたので、内側に一折して審査に臨みました。一般的にはくるぶしが出ている状態が良いそうですが、割と短くした方が格好が良いそうなので、師範のアドバイスを受けて短めにセットしました。
2−2.打つ形(型)を変えた
原因の2つ目、打つべき形を間違えた。
なので審査で打つ形を変更しました!

前回(不合格)私が打った形は剛柔流の「セーパイ」と「クルルンファ」です。
「セーパイ」と「サイファ」に変更した!
特にサイファについて理由は以下のとおりです。
・割と打ち慣れている
・短い形でミスや減点を減らす
・短い形の方が好まれる傾向あり
・審査員はクルルンファは大会等で上級者のを見慣れている
こんな理由から今回は、サイファを選択しました。
前回の記事でも書きましたが、あまり長々とした形で減点を多くもらうよりは短い形をきっちりとこなした方が無難だと言えるかもしれません。
2−3.ごまかさない!しっかりと打った
原因の3つ目、曖昧さや誤魔化しは一切せず
丁寧にしっかりと打った
形の審査は大会で対戦している訳じゃないので「ほらしっかりと打っているでしょ!」と言う感じにじっくりと打ちました。

早い身のこなしや、技のキレや技の見せ方などはあまり意識しないで、一つ一つの技をじっくり見せるように打ちました。淡々と教科書通りに打つイメージです。
よく言われますが、やはり立ち方や挙動のつなぎ方などもしっかりとイメージして打ちました。
つま先の位置は勿論、足の指一本まで見てくる先生も居るので、細かい意識を心がけました。
2−4.形の動きを再チェックした!
原因の4つ目、形の動きを勘違いしていたので、
師範に指示を仰いだ!

自分では上手く出来ていると思っていても、微妙な勘違いとかがあったのです。こればかりはネット上の動画を見ても気が付かなかったり、教範を読み込んでもわからないものもあります。
なのでまずは自身の師範(公認6段)に教えを請います。
忙しい身の上の師範に個別にお願いするのも気が引けますが、わがままを聞いてもらい、稽古終わりに形を見てもらったり、アドバイスを受けました。
ここで指摘された事は公認段位試験だけでなく、普段の稽古や指導にも当然活かせるものです。
2−5.セミナーや講習会を受講した
県連が主催する形のセミナーに参加した
都道府県にもよるかもしれませんが、公認段位試験に向けたセミナーや講習会を行ってくれる連盟もあります。

セミナー等があれば参加するのも一つの手です。
段位審査をする先生や高段位の先生ががポイントを教えてくれます。もちろん全空連の形に準じていますので、段位審査時に役に立つこと請け合いです。
私のいる県では、段位審査向けに直前にセミナーをやってくれるので、とても役に立ちます。県連のホームページに告知されている場合もあるので、お見逃しなく。
セミナーや講習会参加は、審査の上で有利になると思います。
であればぜひ受けておいて損はないと思います!
2−6.教範の本にメモをした
教範にメモ書きをして頭を整理!
おさらいという訳ではないですが、改めて教範を読んでセミナーや師範に指摘された事をメモとして書き込んでおきます。
不思議とメモをした部分は、実際に形を打つ際に頭に浮かびやすいので意識的に打つことができるようになります。

体で覚えるというよりは、頭でも覚えたほうが私の場合は意識しやすいので、バンバン書き込んでいます。別に誰に見せるわけではないのですが、見返すと自分でも再度納得できるので、学生時代の辞書感覚で書き込みました。
実際の形を打っている時に慌てずにすみます。

2−7.立ち振舞も意識した
審査時の立ち振舞も意識する
ということは、前回の審査時に先生が言っていました。
2段を受ける人は、普段の態度や試験を受けている時の立ち振舞も意識してほしいとのことを言われました。見ている先生は見ていてもおかしくありません。

意識の問題かもしれませんが、前回審査時に審査員の先生が言うには、待っている間や入退場に至るまでしっかりとこなして欲しいという事を言われました。
よく言われるのが、終わったあとに知り合いに「どうだった?」「失敗したー!」とか感想を言ったりするのは、非常に目につくそうです。
当落線上にいた場合に、態度が悪いという事で外されてしまうかもしれません。
何より指導者の立場としての意識が低いと見なされる事になると思います。
直接の審査ではないので減点とかは無いかもしれませんが、審査が終わるまでは、油断なく過ごした方が気を張っていて良いかなと思います。
3.終わりに
試験を受けてから一月くらいして師範から合格した旨の連絡を受けました。
一度落ちたので、対策した事の効果があったかと思います。
というか、対策しないと受からなかった気がします。

聞いた話によると、今では5段の先生が何故か2段はなかなか受からなくて複数回受験したなんて事もあったそうです。
学生や若者の技のキレやスピードは出せなくても、形をしっかり打つ事が大事だと言うことを意識して受験すべきかと思います。
また私はコロナの感染症対策で組手は免除でしたが、組手はよく言われるように、以下の点を気をつけるべきだそうです。
・絶対に当てないこと(技をコントロール)
・攻撃を直接もらわないこと(しっかり受ける)
・いろんな技を出すこと(単調にならない)
・試合じゃない(ポイントをとっても意味ない)
・ダラダラやらない!(当てないからと言って技がしょぼいとだめ)
最低でも上記のことは意識して審査に臨むべきかと思います。

ちなみに着替えている時間はないので、形と組手の審査を連続でやるので「形の道着」で組手をやる方が良いと思います。
「組手でアピールしたい」からと思っても組手の空手衣ではなく、形を優先したほうが良いでしょう。
あと、防具(ファールカップや胴プロテクターも)も準備お忘れなく!
人によっては指摘する審査員がいても不思議ではないので!というか、募集要項をしっかりと読み込んでおく事は重要です!
都道府県によっても色々と違うかもしれませんが、公認段位2段の対策として私が行った事を書きました。
何かのお役に立てればと思います。ではまた。
ちなみに2024年現在、私は公認三段です。三段も1回落ちました、、、。
この辺になってくると、なんとなくだと受からないので、対策はしっかりとやる必要があると思います。