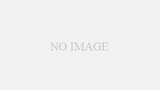空手教室を始めてからやはり怖いのは怪我ですね。
その中で一番怖いのは脳へのダメージです。
あってはならない事故、絶対に防がなくてはいけない事故について、備忘と整理のためブログに書き残しておきたいと思います。
知っておくことは、非常に重要だと思います。
1.空手、格闘技における脳震盪について
よくボクシングとかキックボクシングのテレビ中継を見ていて、相手の攻撃を受けた選手が倒れて所謂KOシーンを見たことが有ると思います。
これは要するに脳震盪を起こしている状態です。
格闘技でなくとも、ラグビーやアメリカンフットボールなどの試合で倒れてしまう場合もこの脳震盪を起こしている場合も有るのです。
所謂脳が揺れた状態で、立っていられなくなるのが脳震盪という事になります。

私の経験では、空手、格闘技をしている時は本格的なものはありません。
キックボクシングのスパーリングでパンチをドンと打たれた瞬間に、一瞬暗くなって膝をついてるみたいな感じなのはありましたが、、。
少なくとも記憶の消失とかはありません。
もしも相手の攻撃がキックだったらどうでしょうか。
キックはパンチの3倍以上のダメージとか言われます。
キックをまともに貰ってしまったら、普通に立っていられないのではないでしょうか。
ハイキック直撃で倒れてしまうのもやはり脳震盪が原因です。
脳が揺れてしまうわけですね。

脳震盪の症状としては以下の通り。
1.頭痛、吐き気、嘔吐
2.目の焦点が合わない。まぶしい光に耐えられない。物が二重に見える
3.耳鳴りがする。大きな音に耐えられない
4.言語、運動反応に遅れる:質問に答えるのが遅い、指示に従うのが遅い
5.意識不鮮明と集中力の低下:虚ろな眼差し、注意力低下
6.不明瞭な発言:流暢にしゃべれない。理解できない言葉
7.共同運動障害:よろよろ歩く、まっすぐ歩けない
8.記憶障害:同じことを何度も聞く
9.見当識障害:変な方向へ歩いて行く、時間、日付、場所がわからない
10.手足に力が入らない、しびれ
11.痙攣
があるそうです。
怪しいと思ったら、速攻で病院に連れて行く事ですね。
自分も意識しますが、救急車を呼ぶ勇気を持ちましょう。
脳に関しては、大丈夫だろうとは思わずに何かある!と用心した方が良いでしょう。
何かあったら事は大事です。
2.応急処置と症状チェック
脳震盪ぽい症状が出た場合にチェックと応急処置方法です。
恐ろしいことに、これらは事故直後ではなくて、少し時間をおいてから症状が出てくる場合もあるので、目を離すのは危険だそうです。
2−1.症状チェック方法
▼精神状態のテスト
見当識: 場所、時間、人、状況を言わせる
集中力: 数字を逆から言わせるなど
記 憶: 前の対戦相手などを言わせる
▼神経テスト
瞳 孔: 大きさ、左右の対称性と対光反射
協調性: 指―鼻試験(受傷者の鼻と検者の指を交互に指で触らせる)
▼運動テスト
歩く、走る
腕立て伏せや腹筋など
上記の事をすることで、症状を的確に抑える必要があるそうです。
よく線の上を歩かせたり、目の前に指を出して焦点が合っているのかを見たりしていますよね。
2−2.応急処置
脳震盪を起こしたら、まずは安静にして休ませ、意識レベル、呼吸、脈拍のチェックを行います。次に頭、頸部のアイシング、そして意識があっても手足の麻痺〈まひ〉がないかをチェックします。意識障害のあった選手に水を与えてはいけません。吐いてしまい、窒息の恐れがあります。
参考抜粋サイト:
ツイッターのフォロワー様より紹介されたサイトです。
非常に参考になります。
脳震盪|SPORTS MEDICINE LIBRARY|ザムスト(ZAMST)
3.セカンドインパクトシンドローム
よく頭を打ったら動かすな!と言うことを聞いたことありませんか?
それは直後という訳でもありません。
24時間〜48時間後に症状が出てくる可能性もあるそうです。

脳は痛みを感じないので、仮に出血していたとしても自覚できる場合がなかったりするようです。
そして出血は徐々に出血している場合は、時間差として症状が現れるそうです。
なので、直後は大丈夫でも、暫くしたら、、、という事になるそうです。
脳がダメージを受けている状態で、2度目のダメージを負うことを
セカンドインパクトシンドローム
と言うそうです。
これは命に直結する話になります。
そして後遺症もより深刻なものになる可能性があるとのこと。
ボクシングで何度もダウンしているのに試合を続行した結果、死亡事故が起こったりという恐ろしい悲劇を招く結果になったりします。
「六三四の剣」のお父さんも作中で死亡するのですが、これが原因です。
子供の頃に漫画を読んでいて衝撃でした。
参考文書:
怪我の対応だけでなく、ジュニアの育成などわかりやす書いてあります。
| ジュニア格闘技・武道「安心安全」強化書 スポ-ツドクタ-が解説 /東邦出版/二重作拓也 | ||||
|
4.脳震盪の予防について
予防と言っても、そもそも偶発的に起こってしまう事だけに予防は難しいのは事実です。でも予防する方法はいくつかあります。
・マウスピースを着用する
・ヘルメットを着用する
・首や体幹を鍛える
・防御のテクニックを上げる
これ以外にも、そもそも体重差の有る試合をさせないとか、脳震盪を起こした人の状態を常に見る事で最悪な事態を避ける事も重要だと思います。

特に防御の練習は重要だと思います。
防御ができていれば、攻撃を喰らわないかクリーンヒットさせない等の多少リスクを減らせると思います。
本当にジムや道場によっては、防御をあまり教えないところがあります。私も実際に防御を教わらずにスパーリングを繰り返し、ボコボコにされていました。
今にして思えばあれは間違ったやり方だと思います。
指導者やその道場によってはそんな事が本当に有るのです。
5.ツイッターで聞いた実際の話
世の格闘家の皆さんや道場はどうやっているのかをツイッターで聞いてみました。
実際の経験や運用方法ですね。
私は経験が少ないため、実際のところは参考になります。
【ケース1】
上段膝を受けて、担架で運ばれるも直ぐに回復、その後妙にハイになった。
1年後偏頭痛がひどくなり、鼻の骨が骨折し、気道が狭くなった為、副鼻腔炎を起こしており、膿が脳近辺を圧迫しもう少しで手遅れと言われた
【ケース2】
倒れ方で判断しています。
棒のように倒れた。また後頭部から倒れた場合も即病院。
【ケース3】
空手の大会ではテンカウントルールなし。
倒れたらすぐにドクターを呼ぶ
【ケース4】
会話をしてみて怪しいかを判断。
また10分くらい後に倒れた場合は、即救急車。
6.終わりに
冒頭にも書きましたが、絶対に起こしてはいけない事故であり、どれだけ気をつけても足りないものだと思います。
実は私は小学1年生くらいの頃、学校帰りに友達と3m位段差のある道路のガードレールに腰掛けていたら、どうやらそのまま転落したらしく、気がついたら母親が迎えてに来ていて病院に担ぎ込まれたことがあります。

友達はピクリとも動かない私を見て、死んだんじゃないかと思ったそうです。
記憶の喪失は恐らく15分〜30分とかではないでしょうか。
当然病院には行きましたが、町医者では何もわからず、翌日大きな病院に行き検査をしましたが異常は無し。
一応無事だったという経験があります。
今更ながら、恐ろしい状況だったなと思います。
当時の私自身は全然大事だと思っていませんでした。何故ならその前後の記憶がないのですから、、。
ただその一件以前は結構勉強ができた気がするのですが、それ以降勉強が苦手になった気がします、、。気のせいかも知れませんが、、。(汗)
参考サイト:
頭を打ったときはどんなことに注意したらいいのですか。/千葉県